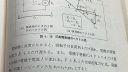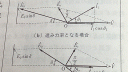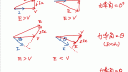フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
管理人キーマスター
こんにちは。管理人です。
電圧管理・運用で私の知りうるところはあまりなく、夜間の軽負荷時間帯には電圧上昇傾向になるのでSHRの逐次投入、明け方にはSHRの逐次開放、徐々に負荷が重くなる昼間帯では逐次SCの投入がさなれ、夜に向けてはSCが抜けていく、連系変圧器のタップは基本的には固定、配電用変圧器(タップ付き)は常に2次側母線を監視して目標電圧が逸脱するたびに自動的に調整されている認識です。また、無効電力調整のため同期発電機(主に火力機)の進相・遅相運転を組合せて系統全体をにらみながら調整されていると思っています。(昔の分散型型電源のなかったような時代は)使い分けとしては配電用変電所の変圧器2次側母線は送電系統から言うと末端なので、1か所の2次側母線電圧だけみて単純に目標値にあうようにタップ切換で調整していると思っています。連系変圧器は1か所の母線電圧だけを見て運用できるようなものではないので系統全体の無効電力調整が主でタップはほとんど使わない(使えない)と思うのですがどのような時に使うのか私もよく存じ上げていません。(変電所の運転は指令を受けて操作するもので・・・。)
近年は分散型電源の乱立でさらに難しいことになっていると思います。
管理人キーマスターおじさんさんこんばんは。色々コメントありがとうございます。
負荷電流による配電用変電所の配電線送出電圧の調整については私も同じような感覚を持っています。負荷電流が増えることによる配電用変電所への到達電圧の低下や変圧器インピーダンスによる電圧降下もあるので配電用変電所6kV母線電圧も下がるので、これをLRTによる巻き数比変更で調整(あげて)送り出すと思っています。
が、これはいままでの標準的な状況で、近年は再エネ(特に太陽光)の配電系統への連系爆増に伴い複雑になってきているようです。H25年頃の再エネの上り潮流が変電所へ逆に上る(バンク逆潮流)の規制緩和により、近年は軽負荷期には上り潮流により配電用変圧器2次側の6kV電圧が上昇しLRTでは電圧制御ができないため、6kV母線へ調相設備(SHR)が必要な状況が出てきているようです。上りを考慮しはじめるとこれまでと逆になってきているみたいです。
また、特別高圧以上の電力系統全体の電圧調整は無効電力制御(発電機の力率制御および調相器)によるものが主なのだと思います。ピンポイントな一か所の変電所の連系母線(77kとか154kVなど)の電圧を変えても系統全体のバランスが取れないから全体の無効電力制御により調整しているのだと思っています(分かってないけど)
ある場所に調相器を接続することで、調相器まで流入する無効電力が通過する電気所全体に影響するので全体をにらむと調相器が便利なのではと思っています。管理人キーマスター上記引用元は「標準電気機器(オーム社)」です。
上記のベクトル図の元の回路図と図記号の与え方は添付のとおりです。でも、鹿の骨さんの書いてくださったベクトル図でも説明もできるし計算もできるように思います。
(進みの時は180°+力率角、遅れの時は180°ー力率角で描けばよいのかと理解しました)鹿の骨さんの少し捻ったものの見方での説明はスゴイといつも思っています。
いつもありがとうございます。ファイルの添付:
管理人キーマスターが、手持ちの書物で調べてみるとまた全然違うベクトル図が。
端子電圧と誘導起電力が逆位相です。
確かに逆起電力だから逆でもおかしくない気がする。しかも無負荷で回転している同期発電機の端子電圧と誘導起電力が逆の位相でないと(打ち消さないと)、VとEに電位差が生じて電機子電流が流れてしまうのでこれはおかしい。
分かったような分からないようなまた混乱しました・・・。
でも同期電動機のベクトル図はいろんな表現があるかもしれないと感じました。ファイルの添付:
管理人キーマスター鹿の骨さんこんばんは。
コメントありがとうございます!
ムムっ!
なるほど!と思った反面、力率-1のイメージ(数式的な扱いで発電と逆の意で便宜的に記載いただいたベクトル図で表現できるのだと受け止めました)が現物のイメージにぴったり合わない(力率1の電動機なのにVと電流が逆位相なのが気になりました)するっと飲み込み切れませんでした><
でも、鹿の骨さんの発想、なるほどと着想しました。
そして、力率角の問題か!とも思いました。冷静に考えると発電方向(送電方向)でのフェランチ効果は進み力率だと受電端が上がる。となると力率角の問題になってきて、発電=必ずE>V、電動機=必ずV>Eではないことに気づきました。
つまり力率角を意識すると添付のようになるのでは、という理解に至りました。
このあたりが同期機のV曲線の仕組みなのか、とも思いました(意味分かってないのがよく分かった気が・・・。)ファイルの添付:
管理人キーマスター鹿の骨さんこんばんは!
コメントありがとうございます。「力率-1.00」
電動機≡負値の電力を発電する発電機電流が逆向いた発電機。
電流ベクトルを発電機と逆に描くのかな。やばい、すぐ分からなそうです(汗)
管理人キーマスター私も今年、甲4類受けてみたいと思っている1人です。
有識者の方おられたらコメント期待しています・・・。管理人キーマスターカモネギさんこんばんは!
2級、おめでとうございます!!
少しでもお役に立てたとすればとてもうれしいです。1級も難易度そんなに変わらないように思っています。ぜひがんばってください!管理人キーマスター最近多少仕事が忙しく、試験勉強する元気がなくなっていてネスペの勉強の予定がずいぶん遅れてます。
試験がまだ遠いからエンジン掛かってないとも言えます。強い味方でもあり、最大の敵でもあるモチベーション、これとうまく付き合わないといけないなと思うこのごろです。
管理人キーマスターわたし、合格へのお役には立ててないと思っていますが、合格待ちまでの間、少しでも気持ちが楽になられたということだったらうれしいです!
みなさまへお祝いのお裾分けしてあげてください(笑)私もエネルギー分けてもらって春のネットワークスペシャリストがんばります!
管理人キーマスター2種合格ですか!
おめでとうございます!
2種、1種は勉強中は高いハードルに感じ、受かる気がしない、合格した時はなんとも言えない気持ちになれる試験だと思っています。合格をかみしめられてください。わたしもパワーもらってがんばります!
管理人キーマスターえびすけさま
コメントありがとうございます!
ipad学習法、とても便利ですよね。
運用開始できてよかったです。
技術士2次!
ハイレベルな試験です。
私は受けることもできないですがぜひがんばられてください!私、上の方へ書いてるとおり、試験の環境に身を置いていないとやる気がでないです(笑)
次の試験まで遠いので最近だらけています・・・。
いまからIPAの高度試験「ネットワークスペシャリスト」申し込みます。
気合入れます。今年もがんばりましょう。
管理人キーマスター3386さんこんばんは。
ぜひ機会がございましたら、よろしかったら共有ください!
サイト上に公開させていただいてよろしかったらみなさんにも有益なものとなると思います。
私、スコット結線理解できていないです・・・(汗)管理人キーマスター3386さん、コメントありがとうございます。
息子さま、私と同じ工業高校生、とっても親近感を感じます。「物理と数学をやると楽しい」
すごく気持ちがわかります。
英語なんて大変な状況でした。いま中一の息子に英語の問題出されてもぜんぜん分かりません(汗)
英語の苦手意識強すぎる状況で、語学の勉強は私にはぜったい馴染まないと感じてるところです。
また、私事ですが以前法律を勉強しようと通信制の大学に入学していた時期がありました。スクーリング等それなりに楽しかったものの、レポートというのが大変だし、いわゆる文系のレポートというのは答えがあるようで無いような感じ、ずーっと答えの明確な学問をしてきたのでこれまたとてもつらく、結局途中やめした過去があります(汗)いまのところ、上にも書いた程度の事務系資格に少し興味があります。
>宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者、社労士とか。ここらは日常生活でも役立ちそうな大人の基礎知識が得られそうに感じまして。
3386さんは幅広なご経験と知識と感じました。今後ともよろしくお願いします。
鹿の骨さんの資料は10年以上前から色々頂戴してとても貴重な資料となっております。
スコット結線の資料は検索も上位に出てくるようになり、多くの方に読まれている資料です。検索順位が低く埋もれている資料もあると思っています。
まだ古いサイトから移植作業中ですが、移植完了したら、一覧のまとめページを整理して新サイト版の電気事典で移植完了させたい予定です。鹿の骨さんの資料はとってもスゴイものが多くありますのでぜひいろいろご覧になってください!
- この返信は11ヶ月前に管理人が編集しました。
管理人キーマスター3386さま
明けましておめでとうございます。
そして電力の安定供給へのお勤め大変お疲れ様です。電気(水とかガスとかもですが)、届くの当たり前でないですよね。
日々の関わる人みんなの力あってです。地熱発電所のお勤め、とても多岐にわたるのですね!
びっくりしました。発電所の運転保守だけでなく、伐採や除雪、なんでもありなのですね。
スゴイです。日々、大変お疲れ様です! -
投稿者投稿